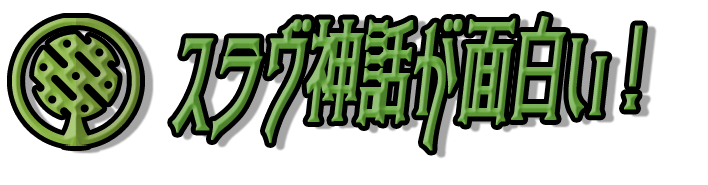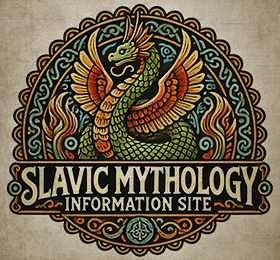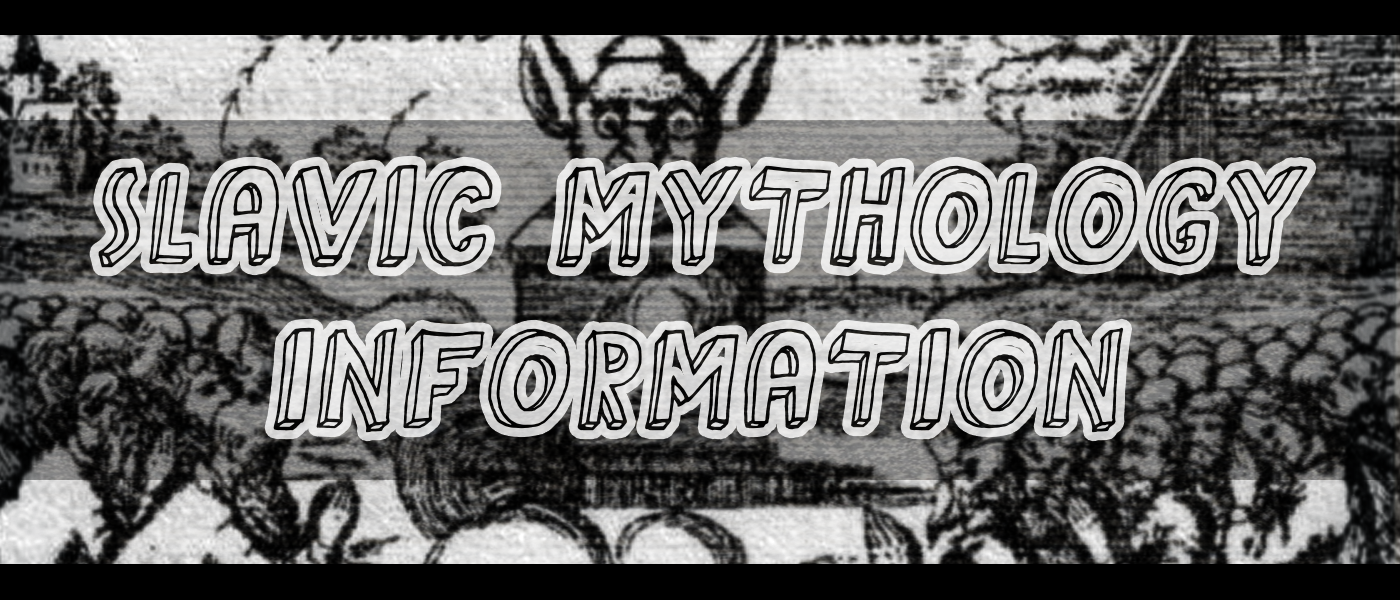
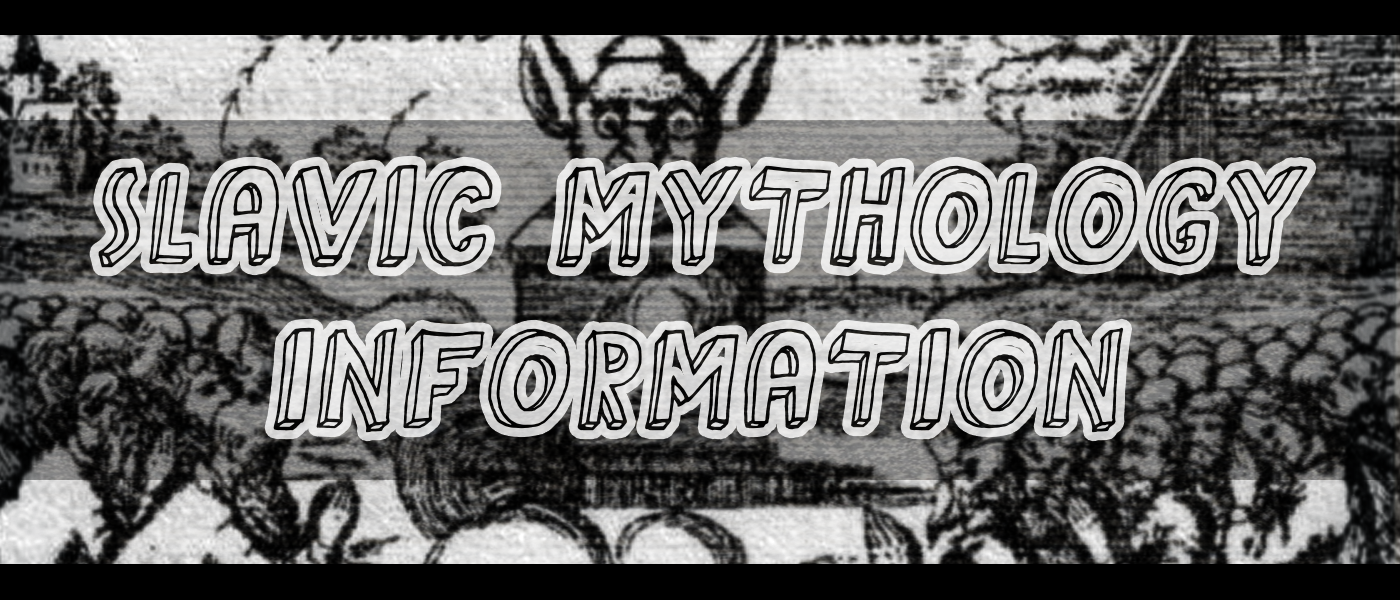
スラヴ神話における「魔女」の種類と特徴
スラヴ神話に登場する「魔女」は、単なる邪悪な存在ではなく、強力な魔術を操る者として畏れられ、時には敬われることもありました。魔女にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる役割を持っています。本記事では、スラヴ神話に登場する魔女の種類とその特徴について解説します。
|
|
|
バーバ・ヤガー
スラヴ神話における最も有名な魔女が「バーバ・ヤガー」です。彼女は森の奥深くに住む老女の姿をした魔女で、「鶏の足を持つ不思議な小屋」に住んでいるとされています。
バーバ・ヤガーは、しばしば旅人や迷い込んだ子どもたちを試す存在として登場し、食人鬼のように恐れられることもあれば、知恵を授ける存在として描かれることもあります。その性格は一貫しておらず、訪れた者がどのように接するかによって態度が変わるのが特徴ですね。正しい作法で接すれば助けてくれることもありますが、無礼な態度を取れば食べられてしまうかもしれないのです。
また、バーバ・ヤガーは魔法の乳鉢に乗って空を飛び、強力な呪術を使うことができるとされています。彼女の知識は深く、勇者が試練を乗り越えるための鍵を握っていることもあります。
ヴェドマ
ヴェドマはスラヴ神話に登場する魔術師の女性で、「知識を持つ者」という意味を持ちます。彼女たちは人々の間で「呪術師」として恐れられ、同時に尊敬されることもありました。
ヴェドマは未来を見通す力を持ち、薬草の知識にも長けているため、病気を治すことができるとされていました。しかし、怒らせると呪いをかけたり、不吉な予言をすることもあります。
このようなヴェドマの力は生まれつきのものではなく、特定の修行や儀式を経ることで得られると考えられており、一部の村ではヴェドマがシャーマン的な役割を果たしていたとされています。
キキモラ
キキモラは、家に取り憑く邪悪な魔女のような存在です。夜になると家の中で奇妙な音を立てたり、住人に悪夢を見せたりして、不安や恐怖をもたらすとされています。
特に、家の秩序が乱れている場所を好むとされ、家が汚れていたり、住人同士が争っていると現れると信じられていました。そのため、キキモラを追い払うためには、家を清潔に保ち、家族の調和を大切にすることが重要だとされていました。
キキモラを防ぐために、家の四隅に塩を撒く、枕の下に鉄の針を置くなどの風習が伝えられています。
ズリツァ
ズリツァは、夜に現れる魔女で、特に赤ん坊や若い女性を狙うとされています。美しい女性の姿をしていることが多いですが、本性は恐ろしい顔であるとも言われています。
さらにズリツァは月の力と結びついており、満月の夜に最も強力な力を発揮すると信じられていました。彼女に狙われた者は、夢の中で彼女と遭遇し、悪夢に苦しめられることがあるとされているのです。
ズリツァから身を守るためには、寝室に魔除けの護符を置いたり、特定の呪文を唱えたりすることが効果的とされていました。
魔女と「変身」の力
スラヴ神話の魔女は、しばしば「変身」の力を持つとされています。
- バーバ・ヤガー:鳥や獣の姿に変わることができ、必要に応じてカラスやオオカミに姿を変えることがある。
- ヴェドマ:霧や影に変身し、人々の目をくらませる能力を持っているとも言われる。
- ズリツァ:夜になると黒猫やフクロウに姿を変え、標的の周囲をうろつくことがあると信じられていた。
このように、スラヴ神話の魔女たちは、ただ恐ろしい存在というわけではなく、知恵を持ち、時には助けとなることもある特別な存在だったのです。
スラヴ神話における魔女は、それぞれ異なる特徴を持ちながら、人々の生活と深く関わっていました。バーバ・ヤガーのように試練を与える者もいれば、キキモラのように災いをもたらす者もいますが、共通しているのは「ただの悪ではなく、知恵や力を持つ存在」として描かれている点です。こうした魔女の物語を知ることで、スラヴ神話の奥深さをより感じることができるでしょう。